面接技術訓練の試み
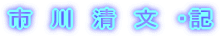
第1 弁護士の法律相談技術の現状
1 見よう見まねですらなかった法律相談技術
弁護士の仕事の出発点は法律相談である。どのような重大事件も、最初は法律相談として始まる。相談者が抱える問題を理解し、解決策を模索し、採るべき手続を検討する。本特集では、そのように重要な「法律相談」に光を当て、必要な技術とは何かを探ることを目的としている。
しかし、翻って考えてみると、このような弁護士にとって最も基本的な法律相談技術について、これまでどのような訓練・教育が為されてきたのかという点になると、弁護士としては、正直、赤面せざるを得ない。これまで、法律相談に光が当てられることがなかったばかりか、その訓練・教育についても、全くといって良いほど、手当が為されてこなかったからである。
弁護士は、司法試験に合格した後、1年半(従来は2年間)の修習を受けるが、この間、弁護士の実務を勉強する機会としては3ヶ月(従来は4ヶ月)間だけである。
この弁護修習期間は、修習指導担当弁護士と行動を共にし、弁護士の仕事の仕方を身をもって体験する。もちろん指導担当弁護士の法律相談の現場に立ち会うことも出来るし、これが原則である。
そして、弁護士が法律相談の現場を見る機会は、ただこれだけというのが、これまでの実態であった。
しかし、この指導担当弁護士も、かって修習生だった頃に、指導してくれた担当弁護士の法律相談の現場を垣間見たことがあっただけであり、特別な訓練を受けたことはない。つまり一種、徒弟制度のようなことが旧態依然と行われてきたが、それもたった3、4ヶ月という短期間、垣間見るだけである。いわゆるイソ弁などの勤務弁護士の場合に、弁護士登録後、若干、先輩弁護士に付いて回る場合もあるが、これも訓練とはほど遠く、五十歩百歩といったところである。*1
2 孤立化した法律相談技術
では、弁護士は、一体どこで、法律相談の技術を身につけているのだろうか。
答えは、自分自身の会話術を、自分自身の判断で、日々、磨いている、ということになる。
自分自身のというのは、弁護士は決して他の弁護士の法律相談を見る機会が与えられないし、他人に見てもらって批評してもらう機会もないからである。
弁護士会では様々な問題についての研修会を開いているが、これらは種々の法律問題についての解説が中心であり、いわば知識に偏した内容になってしまっている。法律相談技術のような、訓練的なスキル収得機会は用意されたことがなかった*2。
その結果、弁護士は、修習時代のほんの一時期に、他人である指導担当弁護士の法律相談を見る機会が与えられた後は、自分の信じる道を、それぞれが勝手に突き進んでいるのである。これに対する批評の機会もなく、他の弁護士に見られることもなく、いわば無批判に放置され、自己流のまま増殖しているというのが、弁護士の法律相談技術の現状である。
したがってある弁護士がある方向に突き進んでいるのに対し、他の弁護士は全く別の方向に向かっているかもしれないし、更に別の弁護士もこれとは異なる勝手な方向に進んでいるのかもしれない。他の弁護士がどのような法律相談をしているのか、そもそも本人以外には知りようがないので比較の方法すらない、というのが正直なところである。
このように、手法ないし技術、あるいは姿勢などというような法律相談をめぐるスキルについては、一切の光が届かない、ブラックボックスのような状況にあるというのが実態である。
弁護士はバッジを付けた瞬間に対等だ、などという言い方がある。先輩も後輩もなく、クライエントのために、対等に十全に活動すべきであるというような場合に使用される。そこまでは良いとしても、同様に弁護士になった瞬間に法律相談技術も一人前とされて放任され、いつの間にか、ベテランなどと呼ばれるようになるということを指しているのだとしたら、極めて非科学的・不合理な、お寒い話である。
3 さまざまな苦情の現状
弁護士会には、法律相談での弁護士の対応について、さまざまな苦情が寄せられている。相談者の権利意識とともに、このような苦情は全国的に激増の傾向にある。
いわく、弁護士が横柄でろくろく話を聞いてくれなかった。怒られてしまい、十分に話が出来なかった。自分は専門外だからといってそれ以上話を聞いてくれない。自分の意見ばかり押しつけるように述べ、きちんと話を聞いてくれない。親身になって話を聞いてくれず、名前を聞いても教えないことになっていると言われた(法律相談センターで)、などなど*3。
その多くは、話を聞いてくれないという点に集中し、また(非常識な)一部の弁護士に集中しているとの情報もある。
しかし、もともと一般の弁護士がどのような法律相談の対応をしているのかが不明であるので、このような苦情の原因や実態、顕在化しない不満や法律相談そのものの問題状況については、個々の弁護士はもとより、弁護士会や法律相談センターにも把握できない、正に手探りの状況にあるのである。
第2 ビデオ教材・事例研究の導入
1 法律相談自体を教材とした訓練の必要性
この特集では、法律相談にカウンセリングの観点からも光を当てようとしている。さまざまなスキルを提案しているが、このようなことを実際に法律相談の現場で使いこなすことには、相当な訓練が必要である。
それは、法律相談は、単なる知識の切り売りではなく、相談者との会話の成立を前提として、相談者の相談内容に入り込んでいくという極めて動的な技術を必要とするものだからである。したがって、弁護士の対応は相談者毎に、事案毎に異なってくるし、事案を離れての一般論としての正解はあり得ない。事案があり、相談者があり、それらの会話のキャッチボールの中で、一枚一枚ベールが剥がされ核心に迫っていくのである。解決の方向についても、事案内容だけでなく、相談者の希望、意思、資力、力量、人間関係などなどの不確定要素まで考慮する必要があるだろう。
このような法律相談の性格に照らすと、訓練は、実際の法律相談の現場を見ながら、その相談の長所・短所を指摘したり、弁護士の発言の目的を探り、それが成功しているか否かを検討するなどの、現場主義を採らざるを得ないものと考えられる。
2 ビデオによる教材の制作
このような法律相談の性格に対応した教材としては、法律相談の現場を撮影したビデオが最適である。
具体的には、たとえば、一般的な法律相談について、分野ごとに、相談の風景をビデオ化し、これをシリーズ化する。当面は、需要の多い、相続問題、離婚問題、交通事故、クレジット・サラ金問題などについてビデオを発行し、順次、増やしていく。
これは、各分野ごとに相談の性格が少しづつ異なるため、典型的な相談分野ごとに教材を制作することが適当であると考えられるからである。
また、同じく相続問題といっても、いくつもの切り口があり得るので、オーソドックスな分野から始め、順次、これを拡大して、何種類かの教材とすることが適当である。
但し、書籍としては法律相談シリーズのようなものが各分野にわたって発行されているが、法律相談教材としては、すべての分野をフォローするようなことは必要ないと考える。あくまでも、法律相談技術が習得の目的であり、個々の相談は素材としての役割が中心だからである。
3 教材ビデオの作成作業
法律相談の現場をビデオに撮影したとしても、これを教材として実際に提供する場合には、事前にいくつかの準備をしておく必要がある。
① 当該法律相談の会話の内容を書面に反訳し、議論の際にいつでも参照できるようにしておく。
② 次に撮影されたビデオを前にして、教材を制作する側のスタッフと、法律相談担当(出演)弁護士とのディスカッションが必要である。
この場合のスタッフとしては、弁護士の他、カウンセリング研究者などの弁護士以外の専門家が入ることが望ましい。相談者の心理状況を的確に把握し、弁護士同士では見落としかねないポイントについての指摘が必要だからである。
相談者の相談目的は何だったのか、この相談目的は、的確に引き出されているか、弁護士の発問の内容、タイミングは妥当だったか、相談者は十分に質問したいことを聞いてもらえたと言えるか、あるいは聞いてもらえたと感じることができたか、弁護士の回答は的確か、相談者は回答を理解できたか、回答に満足しているか、相談に満足しているか、その原因は何か。等々。
その上で、担当者としては、どの点を苦心したのか、どうしてこのような発言に至っているのか、この場所では何を考えていたのかなど、ビデオ教材相談現場での弁護士の意識・思考を可能な限り客観化し、議論可能な状態にする。
また、教材制作側スタッフからは、当該法律相談を見て感じたこと、考えたことを批評として出し、担当弁護士の意識とすりあわせる。更に、どのような改善・工夫が可能なのかについても意見交換する。
これによって、このビデオを教材とした場合の、教育・訓練の使用目的を浮き彫りにできるようになる。場合によっては、教材に適さないことも判明する。
③ これらの作業を前提として、この法律相談ビデオの、いくつかのポイント部分を設け(問題のある部分、あるいはスキルが発揮されている部分、その他教材として強調したい部分)、いつでもこれを指摘できるようにインデックスを作る。頭出しの準備である。ビデオテープでなく、CDやDVDなどのディスクメディアであれば、もっと簡便な利用しやすいものを作れるかもしれない。
④ 更に、これらに基づいて、この教材ビデオの解説を制作する。これは、広くこの教材を使ってもらう場合に、どこで行なっても一定の水準を確保実現するための資料を提供するものである。解説には、前述のポイント部分について、制作者側の制作意図を説明し、どのようなポイントであるかについても説明する。
⑤ なお、事案によっては、相談者が資料を持参することもあるし、人間関係や取引関係などを図式化しないと理解しにくい場合も考えられる。したがって、ビデオ教材には、会話の合間に資料や図表などを挿入することも検討されるべきであろう。
4 実際の利用法
これらを前提として、法律相談訓練を実施する。
訓練参加者にビデオを観てもらい、その後、これに基づいて意見交換・議論をするというスタイルを採る。
このようなスタイルを前提とすれば、訓練にふさわしい人数も自ずから決まってくる。つまり、自由に意見交換出来る人数としては、数名ないし多くても20名程度が妥当だろう。また、様々な意見が出ることを期待し、参加者の経験年数もある程度のバラツキがあった方が効果的かもしれない。そして、この解説書に書かれていることを少なくとも理解できている法律相談訓練のベテランがチューターのような立場で参加できればなお良いだろう。
なお、実際の意見交換・議論の場では、必ずしも教材解説書に従って行う必要はない。参加者から自由に意見が提出されることの方が重要だからである。いわば、参加者1人1人が、自分自身の法律相談体験と照らして教材ビデオを鑑賞し、自分ならこうしたという能動的な批評思考を実現することで、教材としての力を発揮できるものだと考えるからである。
したがって、教材解説書の指摘は、参加者の意見が偏っていたり、問題点に思い及ばない場合に、水を向ける形で利用することが適当であると思われる。
また、当該訓練の場で出された意見は、ぜひ集約の上、当該ビデオの解説書の充実のためにフィードバックして役立てられるべきだろう。
5 弁護士以外での使用法
ここでは、弁護士の訓練法としてのビデオ教材について述べてきたが、この教材は弁護士以外にも教材として有効である。
たとえば、日常的に住民の相談に応じている社会福祉協議会の相談員などから、基礎的な法律相談の内容や方法についての指導を希望されることがあるが、現在、適当な教材がない。このビデオは、このような場合の教材としても使用することが出来る。
さらには、大学で、学生たちが法律の勉強をする場合でも、生きた法律を学ぶための教科書として、恰好のものとなる可能性がある。
但し、弁護士以外に向けた教材としては、法律相談スキルという観点よりも、むしろ法律の実際の生かし方などという、動的な視点をもちつつも、あくまでも法律教材としての意味が大きいと思われる。したがって、解説書も、これに応じる形で、弁護士の質問の法的な意味や、弁護士が使った法律用語の解説などの、法的知識に亘った解説が必要になるだろう。これらは、反訳書の脚注などの形で実現されても良い。
もとより、一般市民が、書籍としての法律相談シリーズを購入するような意味で、これらのビデオ教材を使用しても良いだろう。但し、これは、流用であって、ここに照準を置くことによって、本来の弁護士用教材としての目的が妨害されることは避けなければならない。
6 どうして生か
ビデオ化については、シナリオを作成し、弁護士役と相談者役が相談風景を演じることも可能である。その方が、質問事項が的確であったり、当然、回答の法的ないし技術的的確性も担保できることとなる。
しかし、第1に、これでは作られた法律相談でしかなく、シナリオライターの狭い経験の上での問題意識しか反映できない。
第2に、さまざまな資質の相談者に対しての対応は千差万別であり、この微妙な呼吸こそが法律相談には求められており、ここを捉えるためには生であることに意味がある。
第3に、回答の法的正確性を確保するためには、事前に大凡の質問事項を回答者に知らせておく外(これについては異論もあり得るかも知れない。検討課題である)、収録後に複数弁護士のチームでチェックして問題のあるものは刎ねることとすればよい。
したがって、ビデオ化には、収録した相談の中から、後日、ふさわしいものをピックアップする作業が必要であり、実際に使えるものという意味では、歩留まりは数割程度になるものと思われる。
7 プライバシーの保護
生の法律相談を収録する場合には、当然、相談者のプライバシーの保護が問題となる。場合によっては、この問題だけで、生相談を断念せざるを得ないことも考えられる。
これについては、(ア)相談者に事前に趣旨を説明して了解を得ること、(イ)相談において固有名詞を使用しないようにすること、(ウ)撮影については顔の撮影を工夫すること、などの配慮をすることで、クリアできるのではないかと考える。
また、顔の撮影については、原則として弁護士のみとし、相談者は顔を撮影しないか、後でぼかしを入れるか、更に後記のような相談の図解との併用をするか、工夫する。
8 相談時間
法律相談には、弁護士会によって、あるいは相談の種類によって、相談時間が区々になっている。したがって、スタンダードなものとして、30分もの、1時間ものの二種類を作成することが適当である。
通常は、相談時間が30分程度に限定されていることが多いので、この時間内で、どのように効率よく法律相談を実施するかを示すということで、30分もの。1時間ものについては、時間をかけてきちんとした相談を受ける場合のスタンダードという趣旨である。
9 相談担当者
相談担当者は、各分野ごとに造詣の深い弁護士、あるいは他の弁護士の参考になるようなベテラン弁護士が考えられるが、単なるお手本ではないので、経験数年ないし10年程度の弁護士が担当することも検討される。
さまざまな批評に晒されることになるし、場合によっては批判にわたるようなこともあり得るので、教材になる弁護士の確保が実は最大のネックになりかねない。これについては、研修委員会などを中心に人材を確保することが必要である。
第3 まとめ
弁護士に対しては、さまざまなイメージが一人歩きしてきた。敷居が高いことに始まり、どこに行けば弁護士がいるのか分からない、料金が不明である、恐い、どんなことを頼めるのか分からない、どんな相談に乗ってくれるのか分からない等々。
その多くは、広告規制などの弁護士情報の開示制限に起因してきたものである。
しかし、翻って考えてみると、法律相談という弁護士実務の第一線部分自体が、個々の弁護士に任せきりに放置され、弁護士同士ですら互いに秘密のベールに包まれてきたという、悪しき職人主義的な独善状況が、このような弁護士像の醸成に関係してこなかったとは言い切れまい。
必要に迫られる中で、いつの間にか高度な相談対応技術を身につけている弁護士もいるだろうが、その裏で様々な弊害も生まれてきた。ビデオ教材の開発と利用の実現によって、科学的な訓練と評価の技術を導入することは、弁護士業務の標準化、水準の維持向上にとって、不可欠な道程であると思われる。
| 至文堂『現代のエスプリ』415号02年2月1日発行所収 |